YouTube学カフェ
鹿児島を拠点とするYouTubeチャンネル「学カフェ」は、現在チャンネル登録者数が1万2千人を超え、県内外から一定の注目を集めています。
しかし、その内容は一言では語り尽くせない独自性を持っており、保守的な主張から陰謀論、排外主義など、大丈夫か?って話題も多くあります。さらには参政党や「やめ参(=元参政党支持層)」、保守党に、新興政党など新しい政治的立場をめぐる言説まで、多様な意見と人たちが集まっては、ケンカしたりしています。
現在の社会は、YouTubeやSNSといった個人発信のメディアが、ますます社会の言論空間に影響を及ぼすようになっています。
いまや、政治やニュースもテレビではなく、YouTubeの話題を起点に動く場面が増えてきました。
そして、その空間を巧みに活用しようとする、いわゆる“妙な団体”や“急進的な政党”も少しずつ姿を見せ始めています。
なかには、発信の過熱が原因となり、精神的に追い詰められた人が命を落とすという痛ましい事件さえ起きています。
こうした社会状況の中で、「個人が発信すること」の意味が、あらためて問われています。
特に、地方という「声が届きにくい場所」から発信する意義とリスクについて、今こそ丁寧に議論する必要があるのではないでしょうか。
登壇するマンガ家の厳男子さんが(一時)はまっていたときがあるらしく、その魅力、問題点、やばさ、ひどさ、中毒性について語ります。
その他登壇するのは、「学カフェ」の主催者・上野康弘氏、出演経験のある鹿児島市議・のぐち英一郎氏、やうやう編集長の土屋耕二も、自身のコラボ出演やコメント欄での応酬をふまえつつ、この場の特徴と地域社会への影響について考察します。
地方における言論の場はどうあるべきか?
情報発信は誰のため、何のために行うのか?
学カフェのようなチャンネルは、地域にとって“希望”なのか、それとも“課題”なのか?
地方からの情報発信にYouTubeは大きな可能性を持っています。
だからこそ、「学カフェでいいのか?」という問いを真剣に立てることには意味があると、私たちは考えます。
単なるチャンネル批評を超えて、これからの地域と発信、そして社会のつながり方について、参加者の皆さんと一緒に考える時間となれば幸いです。
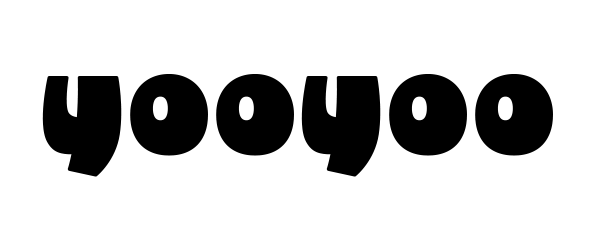
コメントを残す