19号掲載

――かのや乳児院を立ち上げたのはご家族だったとか?
寿のリンガーハットのところで祖父が小児科医をしていました。1947年に児童福祉法が施行され、戦後の復興期に戦争孤児たちの受け入れ先が必要になり、祖父に白羽の矢が立ち、1949年に乳児院を開設することになったんです。
――こちらでは、何歳の子どもたちが暮らしているのですか?
基本的に0歳から2歳までの乳児が対象です。2歳までに家庭に戻る見通しが立たない場合は、里親家庭や児童養護施設へと移行します。
現在は「家庭養育優先の原則」が打ち出されており、可能な限り家庭での養育が推奨されています。その結果、全国的に乳児院を出た子どもたちの約四割は実の家族のもとに戻り、3割弱が里親家庭に迎えられています。
――日本は里親が少ないと聞いていたので、3割という数字に少し驚きました。
鹿児島県内においては、乳児院や児童養護施設から里親家庭へ移る子どもの割合は全体の約16%にとどまっていますが、うちは里親さんとの連携に力をいれていて、支援体制も整っています。
――どんな方が里親に?
本当にさまざまです。実子がいるご家庭もあれば、年齢を重ねてから入籍されたご夫婦、妊娠をあきらめて里親を目指されるご夫婦などもいます。ただ、里親の研修は5日間と非常に短く、それで親としての準備が整うわけではありません。特に2年ちかくを乳児院で過ごした子どもたちは、職員に深く愛着を抱いているため、新しい環境になじむには時間が必要です。
私たちは段階的に里親子の面会交流やお家への泊まりなどをして、子どもと里親の関係づくりに時間をかけています。中には、北薩や離島から通ってくる熱心な里親希望者の方もいらっしゃいます。
――最近はAmazonと連携した支援もされているとか?
はい。「欲しいものリスト」を活用して、それぞれの施設が今必要としている物資を支援してもらえるようにしています。これまでの「寄付」という形とは違う、より自然で温かな取り組みになっていると感じています。
――最後に、この鹿屋や鹿児島という地域について、思うところを聞かせてください。
鹿児島県はよくやってくれているとは思いますが、国のこども家庭庁が出す通達はあくまで「指針」であり、実際に実行するのは自治体ごとの裁量に任されています。他県と比べて予算面で十分とは言えない部分もありますね。子どもたちの未来を考えれば、もっと行政が踏み込んで支えてくれることを願っています。
文・やうやう編集部
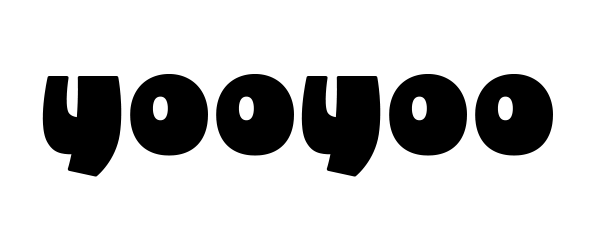
コメントを残す