(11号掲載)
小学生のとき、鹿児島について二つのことを知っていた。一つは幕末の志士をうみ、単独でイギリスと戦争をするような勇猛な歴史。もう一つは薩摩揚。いつか前者については語るだろうから、今回は薩摩揚をとりあげたい。
私は小学生の時にたまたま読んだ向田邦子にとてもはまってしまい、『父の詫び状』を何度も読み直していた。そこに収められた短篇に「薩摩揚」というものがある。
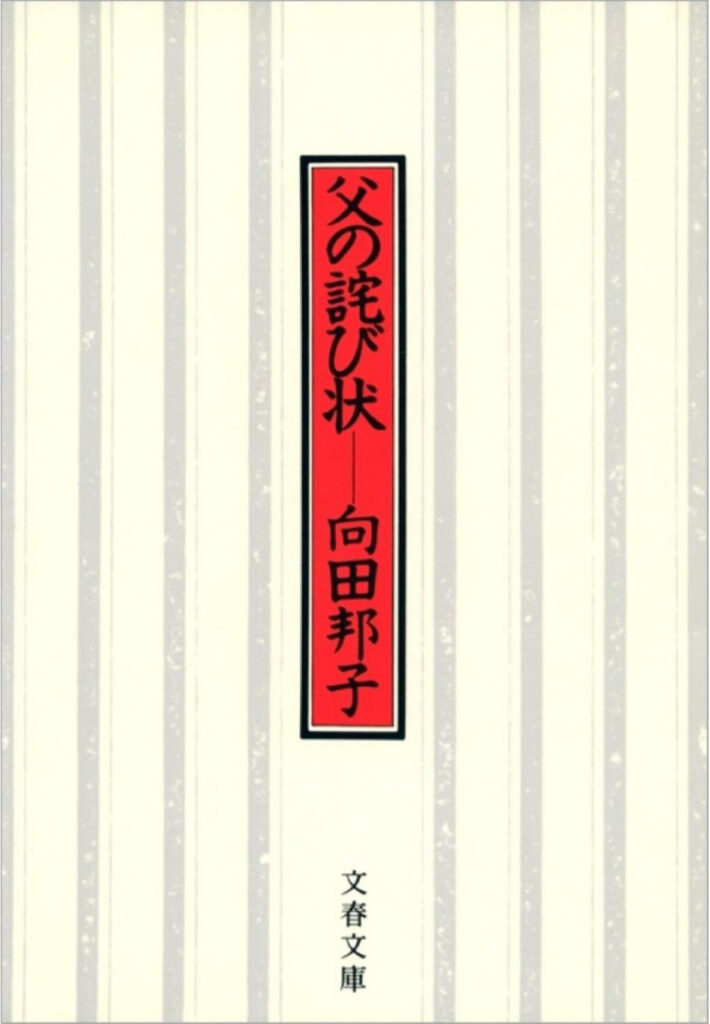
邦子は小学校三年生のときに転勤で鹿児島に訪れた。昭和十四年から三年間、鹿児島市で暮らしていたという。彼女は都内で薩摩揚を見つけるたび、そこでの暮らしを思い出したそうだ。当時、鹿児島の人は同じものをつけ揚げと呼んでいたそうだが、いまはどうだろうか。彼女にとって鹿児島は、子どもの頃にとりわけ印象が強かったようで、『父の詫び状』の他のエッセイと合わせて三十一回も鹿児島という言葉を使っている。
このように、彼女にとって鹿児島が特別だったのは、灰と生理の予感のためだった。
桜島は当時も今と変わらず火を溜め込んでいた。口数の少ない布団屋の少女が、とりわけ降灰がひどく、布団に灰の積もった日、邦子に困ったように笑った顔を見せたそうだ。灰はふだん見せないものを見せてくれるものだった。
彼女の父が仕事の付き合いの飲みで芸者遊びをした帰り、見送りについてきた芸者衆を家にあげてもてなしたことがあった。父はそんなことをする人ではなかったので、邦子は好奇心が抑えられず茶の間から観察していた。そのときに祖母が火鉢の灰をならしていたことが、別の女を連れてこられた挙句、もてなすことに苛立っていた母の記憶と同時にしっかりと書き留めてある。灰は何か特別なことが起きた時のしるしなのだ。
一方で、芸者に苛立つ母を見るその目は、邦子が思春期に入ったばかりだった当時の心情を鮮やかに描いてもいる。十歳から十三歳にかけて、それまでは大人の本だった漱石や明治や大正の文学を読み耽っていた邦子は、自分が大人の世界に足を踏みいれようとしていることを自覚していた。
ある時、鳥集神社の神主の娘と賽銭箱の横に腰を下ろして雑談している時に、その娘が「お姉さんたちのすぐあとご不浄に入るとねえ……」と邦子に話したそうだ。つまり、生理が来た姉たちの様子を聞かせたのだ。邦子は、大人になると面倒なことになるらしい、と初めて生理を予感した。しかし、一方で彼女はしきりに賽銭箱の中身を気にして、こんなに少なくて神社の商売が成り立つのか、とまったく的外れなことに思いを馳せていたそうで、邦子は子どもらしい感覚をユーモラスに描いている。
そんな「薩摩揚」を、当時の彼女がそうだったように、私は十歳を過ぎた頃に読んでいたので、邦子の見ている世界に自分を重ねていた。それからしばらくして、二十八歳になった時、九州を車で一回りする旅をした。その時、熊本から天草を目指していた都合で、鹿児島の出水に一泊した。宿泊したホテルのレストランで、せっかくだし現地で薩摩揚を食べようと思ったが、お店で調理されたわけではなく市販のものを出していたようで、東京で食べたときと何の味の違いもなかった。鶴乃泉を飲みながら次の日の天気を確認したが、桜島は実に静かで、灰は降らないらしかった。家から遠くまで来て、とても歳をとったような感じがした。

文・米原将磨
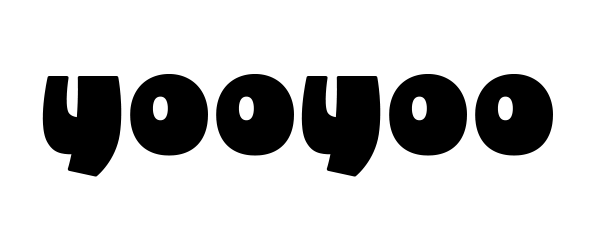
コメントを残す