(12号掲載)
「天領日田」は九州でも名高い美名だ。天領とは江戸幕府の直轄領のことで、日田の地域の一部が天領だった。ただ、注意したいのは、日田の一体全てが天領ではなく、ごく一部の地域が天領であっただけで、いま街の中心部となっているところは天領ではなかった。天領ならざる日田もあるのだ。
そんな日田の中心で生まれた、広瀬淡窓という人がいる。一七八二年、豊後国、つまり現在の大分県の日田で生まれた。商人の家の子だったが、徂徠派に学び、『迂言』(一八四〇年)で藩政改革を提案するなど政治的な発言を積極的にしていた。病弱だったこともあり、家業は弟に譲り、本人は二十四歳より、専ら私塾「咸宜園」での教育を生涯続けた。「咸宜」とは「ことごとくよろし」の意味で、身分に関係なく門下生を迎え入れた。靖國神社に立つ銅像の名前として知られることの多い大村益次郎もこの塾の出身である。そのほとんどが町人で占められた咸宜園は、幕府からの補助金は一切ない塾生の納金だけで運営されていた民間教育組織だった。
咸宜園の名が残っているのは、何よりも三奪法と月旦評という江戸時代においては特異な二つのシステムをもっていたためである。当時の多くの思想家が朱子学や陽明学といった儒教文化に基づいていたのは、日本の生活感覚としての家柄主義や年長者を優遇する文化と親和的だったからだ。しかし、淡窓はこれを良しとせず、入塾した者にはまず、年齢・学歴・門地といった日常生活の中で作られた階級を捨てさせた。そして、そこに実力主義による別の階級を用意した。それが月旦評である。成績順がそのまま席順となった。これは身分制を重んじた当時の風習に反した過激なやり方で、行政干渉を受けるほど当時は政治的緊張感があった。
この日田に生きた変わり者の知識人のもとを訪れた別の変わり者がいた。頼山陽だ。一七八一年大阪に生をうけ、広島に儒学者として登用された父について広島で子ども時代を過ごす。江戸に遊学したのち、脱藩して京都への出奔をしたものの、発見されて広島の邸宅内に軟禁された。解放後に京都へ再度出奔。破天荒な男だった。
酒飲みには「剣菱」の「兵用ふべし、酒飲むべし」のコピーライトの作者、といえば伝わるだろうか。文学史においては、『日本外史』という幕末の革命家たちに非常に読まれた本を執筆したことで知られている。当時、歴史書とは、いま存在している幕府に対する評価に繋がる危険な書物の一つだが、頼山陽は幕府に対して肯定的な歴史観を提示していたつもりだったそうで、『日本外史』は時の老中松平定信に献呈された。その本が討幕を志す者たちにまったく違う形、すなわち尊王攘夷の意味で解釈されたのは歴史の皮肉だろう。そんな頼山陽が九州を旅した時に訪ねたのが淡窓だった。一八一八年のことだ。ほとんど同い年ではあるがおよそ生き方の異なる二人がどのような会話をしたのだろうか。その記録はほとんど残っていない。このように、当時の西日本の知識人ネットワークの重要人物だった淡窓にまつわる史跡、つまり旧家や咸宜園は日田に訪れるといまでも観光することができる。
しかし、実際のところ咸宜園で観光が成り立つはずもない。いまは、温泉・酒・日田焼きそばというB級グルメで知られる。
日田焼きそばなのだが、少し固めの麺を使っているのが特徴的だ。とくにレシピが統一されているわけではなく、麺の感じがざっくりと日田焼きそばを規定しているらしい。

また、日田の周りの山中には、温泉が点在している。そこに行くがてらそれほど観光に寄与しているのかわからないが、日田は『進撃の巨人』で知られる諫山創の出身地であるので、「進撃の巨人 in HITAミュージアム」に出会うこともできる。
日田はこのように特異な人物を輩出してきたのだが、同地を訪れるとその理由もわかる気がする。山中にある日田は街の中心や外縁に川が流れる水郷だ。そして、山に囲まれ、外界は遠い向こう側のように感じるが、豊かな資源を背景に経済的には恵まれた時期が長く続いた。だから、諫山は『進撃の巨人』で一見して壁に囲まれた箱庭を描いているように見えるが、日田に行けば、そのような世界の見方のほうが自然に思えてしまう。そして、咸宜園が行政に干渉されながらも独立できたのは、政治の場所から遠く隔てられていたからだろう。だが、ここから世界に羽ばたいた実業家やクリエイターは同じような人口の街に比べたら多い。
最後に筆者のおすすめを述べると、慈眼山永興寺だ。永興寺は山裾を切り開いて建てられた寺で、街中から少し歩いていくと、日田の美しい街並みを見下ろすことができる。私が訪れた昼時には鐘を叩くことができた。残暑に涼やかな鐘の音が響いた。

文・米原将磨
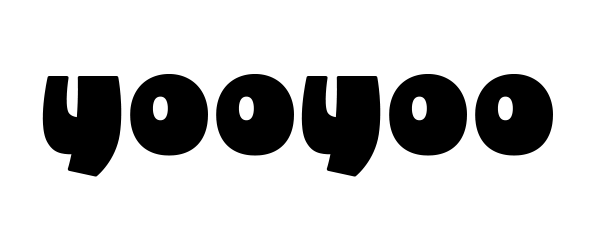
コメントを残す