(13号掲載)
私の数多い趣味のひとつにネットの動画を聴くというものがあります。動画を「聴く」と書いたのは、本業の飲食業が立ち仕事で耳が空いているので配信がちょうどいいからです。(お客さんがいるときはもちろん聴きませんが)
そんな私が聴く動画はYouTube、ニコ生、シラス、ビデオニュース、文芸春秋のウェビナーから、単発のトークイベントまでとにかく幅広く課金して聴いています。
そんな動画視聴ライフのなかで、「幼少期の体験や習慣が、その子の一生を決める。」「最新〝タイパ最強〟勉強法」というニュースピックスの動画がありました。これは先の都知事選にも立候補したAIエンジニアや、16歳で東大に合格した韓国人などが出演して、子供時代の勉強方法や、AIを利用した現代のコスパ勉強法を語るというものでした。
番組の内容を少し紹介すると、「東大に行きたければとりあえず、過去15年の過去問題集をひたすら解いていく」すると、この問題は出る、この問題はでないと抽象的にわかってくるというものや、AIを使った英語の学習方法の紹介などでした。(あとマンガドラゴン桜はみんな読んでいた。)
特に面白かったのはAIでの英語の勉強法です。日本語で話したものを英語に翻訳、自分の英語でおかしい部分をAIから指摘、ショッピングや家族団欒など場面を想定しての会話練習などでした。AIはかなりの精度で会話と改善点の指摘ができて、率直にいって驚きました。興味ある人はぜひ見てみてください。
ただ、番組タイトルにある子供の一生を決めるような決定的なことが語られているかと言えば、さすがにそれはなく、そこにあるのは効率的な試験勉強くらいなものでした。さらに言えば、そもそも子供の一生を決めるようなものが本当に存在するのでしょうか。番組ではタイパのいい勉強法がそれだと言いたいのかもしれませんが、究極まで複雑系の人間の人生において、そんなことがどれだけ妥当性があるのか疑問です。
私がこの話で思い出したのは、最近の料理界で昔のような修業はいらないのではという議論です。たしかに、私が修業していたときは最低賃金をはるかに下回る給料と、殴られながらの長時間労働が当たり前という雰囲気が料理界の一部(私の修業先も)ではありました。さすがに現在はそのような修業の仕方はほとんどなくなっているようですし、そのような環境では若い人が入ってくるはずはありません。あまりにも非効率です。私としてもそのようなものを取り戻すことが必要と思っているわけではありません。
ただ、私はどうしても引っかかることもあるのです。私はこれまで16年間飲食店を経営してきたのですが、あのつらい修業時代を乗り越えることができたという経験が、いまの自分を作ったなという実感があるのです。
「あ、それグルーミングだから」と一部の人は言うでしょう。(※グルーミング・・・何かの被害を自分の中で正当化してしまい、加害者なのに信頼し搾取される構造のこと)たしかにその指摘が合っているのかもしれません。何事も気合いと根性と思ってるところがある私は、そのことで限界も感じているし、これがなければもっと効率的に仕事ができて成功もしたんじゃないかと考えることもあります。
ただ、私も46歳になり、店もこの町で長くやってる方に入ってきました。今さらそんなこと言われてもどうしようもないし、私のなかでは辛い修業時代の経験と気合いと根性で、これまでの苦しい経営の日々を乗り越えて来たという手応えが間違いなくあるのです。
それに加えて、料理人は料理だけできてもやっていけません。お客さんや同僚たちとコミュニケーションをとりながら仕事をしないといけないし、料理の本などを読んで常に勉強も必要です。店を経営するとなるとそれなりに現実の数字をみながら合理的な判断が求められますし、社会のことも勉強しておかないといけません。一言でいえば「人間力」みたいなものが必要です。 その「人間力」は、子供のときにタイパなどを気にしているようでは、身につくとは思えないというのが、これまでタイパもコスパも考えてこなかった、バカな男の独り言です。
そんな、タイパの悪い人間たちが集まって作っているやうやうです。13号もどうぞお楽しみください。
文・土屋耕二
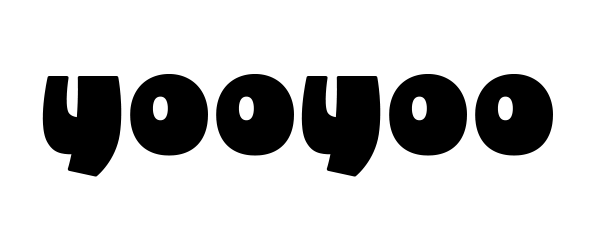
コメントを残す