(15号掲載)
ぼくはこの前、紅葉真っ盛りの秩父を訪れた。秩父市は、埼玉県の南西部に位置する市で東京都の奥多摩がある北西部と接している。東京の池袋からは西武鉄道の特急ラビューに乗れば、1時間半近くで行くことができる。なので、東京に住んでいる子供がいる家族やカップルなどが少し遠出をしたいときに、気軽に行ける場所として利用されている。少し乱暴な言い方をすると、ちょうどいい田舎と言ってもいいかもれない。自然が多いが、交通の便はよく、かといってビルが立ち並んでいるような都会ではない場所としての秩父。
みなさんは秩父ときいて、どのようなことを思い浮かべるだろうか。馴染みのないひとには、イメージがつかないかもしれないが、アニメが好きなひとがいれば、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』などの脚本を担当した脚本家の岡田麿里の出身地だといえばピンとくる方もいるかもしれない。数々の岡田麿里作品の舞台は秩父とされていて、アニメ好きには聖地として知られている。だが、それよりも日本史で誰でも1回は聞いたことがあるであろう日本で最初の流通貨幣と言われている和同開珎がつくられたとする和銅遺跡がある場所という方が多くのひとにとっては、多少はイメージがつきやすくなるかもしれない。なので、秩父は昔はよく銅が採れる場所として知られていたようだ。またこれを読んでくださってる方のなかで歴史好きの方がいれば、政治学者の原武史が埼玉について言及している『〈出雲〉という思想』などの歴史を思い浮かべるひともいるかもしれない。
『〈出雲〉という思想』では、明治以降の近代日本の中心となった天照大神(アマテラスオオミカミ)を祭神とする〈伊勢〉=国家神道に対して、そこから排除されたオルタナティブとしての大国主神(オオクニヌシノカミ)を祭神とする〈出雲〉の系譜を辿るもので、埼玉を後者の〈出雲〉系である氷川神社が広く分布する地域として注目した著書である。このように埼玉は今では東京のベッドタウンのような扱いをされているが、和同開珎をはじめ、古くからの歴史を残した場所なのである。また原はネット配信の鼎談のなかで松本清張の『神々の乱心』をとりあげ、月辰会という秩父宮を昭和天皇にかえて天皇に据えることを目指す団体が描かれていることをあげ、松本清張が日本近代史の裏側を踏まえたうえで「東京に対する埼玉の反逆」を描いたものとして解釈できるだろうとした。秩父は昭和天皇の弟であった秩父宮ゆかりの地でもあった。このように秩父は近代日本のオルタナティブな可能性を考えるうえで重要な場所であるといえる。
日本近代史の裏側ということでもうひとつ付け加えると、秩父にはオオカミ信仰がある。秩父の神社の多くでは大口真神(おいぬ様)が祀られている。例えば、三峯神社(みつみねじんじゃ)では狛犬の代わりに狼の像が鎮座している。これはかつて日本に生息していた狼(ニホンオオカミ)が神格化されたものであり、盗難除け・魔物除けとして信仰されている。縄文時代にもニホンオオカミの牙や足の骨などを身体の一部をお守りとして身に着ける風習があったという。このように秩父の地では古くからオオカミ信仰があったと考えられる。これが山へ籠もって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする修験道などの山岳信仰とも結びついていた。オオカミ信仰があるところは山深いところが多く、修験道の修行場として知られていた。しかし、明治維新とともにオオカミ信仰が盛んであった秩父や奥多摩を含むかつての武蔵国が消え、明治5年に修験道禁止令が出されてからは、衰退してしまった信仰である。
このように秩父は今では、東京のバックヤードのような存在になっているが、近代日本の裏側である〈出雲〉の系譜やオオカミ信仰といった古代日本の流れを汲むオルタナティブな日本の可能性を考えるうえで重要な土地だといえる。都会の喧騒から離れると、時間がゆっくり流れていくのを感じる。ぼくは秩父の奥深い山に映える紅葉をみながら、遠い昔に思いを馳せたのであった。
文・hideaki
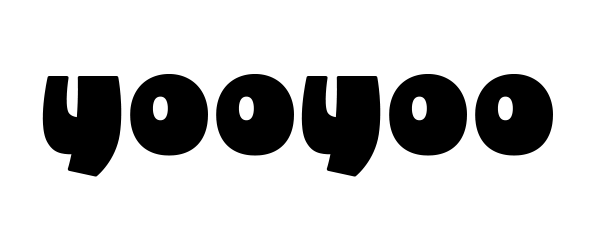
コメントを残す