国鉄・大隅線と志布志線に一回だけ全線乗車したことがある。それは廃止前の夏休み、昭和61年。私は中学2年生で、父と弟との三人での旅だった。将来、鹿児島を探訪しながら生活するという趣味なのか仕事なのか境目のない仕事をするとは想像していない頃なので、停車する駅という駅を写真に収めて記録するような行動には結びつかなかったが、それでも駅や風景は記憶としてかすかに残っている。そのような私が通過した経験のある駅のひとつが志布志線の岩川駅である。
最近、地元の方からの情報により、岩川駅には鉄道記念室があることを知り、その室のある曽於市商工会大隅支所を訪れた。支所の建物の一角が、それに充てられており、想像以上にきちんと資料が並んでいた。そこにある資料のなかで私は「岩川駅史」に一番魅かれた。駅史は、営業している駅の記録帳簿のようなもので、駅従事者が書き足して引き継がれていくもの。つまり他の情報源にないような駅の歴史が濃厚に詰まっているといってもいい。引継ぎなので、記された文字の具合が少しずつ違い、時には癖が強すぎて読めないこともあったりする。でも岩川駅史には、旧大隅町の中心市街地であり、加えて国や県の出先機関が設置されている状況を考えるなら曽於郡の中心地でもあるような「岩川」という町の個性が詰まっていた。お伝えしたいことは山ほどあるが、やはり「弥五郎どん祭」における駅の対応に注目してみたい。
現在は11月3日の祭日に開催される鹿児島三大行事のひとつの「弥五郎どん祭」は、駅史によると戦前は11月5日の開催と決まっていたようである。また、その祭の記述としては「八幡神社祭典 俗称弥五郎ドント云ヒ戦勝ノ神トシ近郷ノ崇敬厚ク尚祭典当日ト翌六日ハ神社附近二農具市ヲ開設ノタメ両日共殷賑ヲ極ム」とある。大隅半島を代表する祭だけに祭日当日の駅利用者は多く、それに臨時車両を出したり駅員を増員させたりしながら対応したとある。また、弥五郎どんが戦勝の神として信仰されていた点にも注目したい。そのためか岩川駅の乗降人員は、日中戦争が勃発した昭和12年以降、急速に増加している。昭和12年の祭典当日が1117人であったのが、昭和15年には2058人となっている。
戦勝の神に願いを込める人々がいたということなのか。そして昭和17年から19年までは空欄となっていたことから、この期間は祭事も中止であったことが理解できる。また昭和20年の乗降人員数の欄は空欄となっていたが、摘要には「終戦直後ノタメ列車運休シ乗降人員無シ」とあることから、祭事は行われたものの鉄道は休止状態であったことが理解された。
注目されない資料からも地域の様々な過去が浮上する。そのような経験を求めて大隅半島の隅々をぶらぶらしようかな。これからも。
文・東川隆太郎
NPO法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事。鹿児島県内の歴史や地理について、多くのメディアに出演し、自ら案内人として地域を語る。かごしま国体では天皇皇后両陛下のフェリーでの案内役もつとめた。
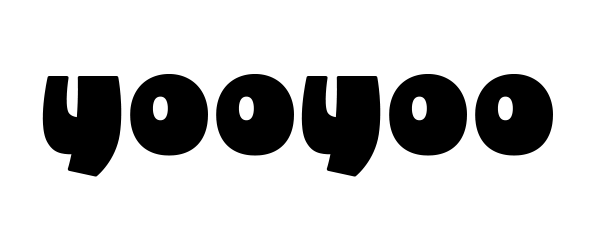
コメントを残す