■電話と直接会う文化が、チームの生産性を下げている?
文:鹿屋ライフハック太郎
「やっぱり直接会って話した方が早いよね」
そう言われて、なんとなく同意してしまうことありませんか?
でもそれ本当に早いですか? あるいは、ただ「責任の所在を曖昧にしておきたいだけ」かもしれません。
■電話や会議が好きな人たちの正体
電話や“ちょっといいですか”から始まる口頭のやり取り。
これを多用する人たちは、「人間関係」や「その場の空気」で仕事を進めるのが得意な人たちです。
逆に言えば、それが通用しない場面では力を発揮できないことも。
一方で、Lineやメール、タスク管理ツールでやりとりする人たちは、記録に残し、論理的に話を詰めていくスタイル。
「ふわっとしたやり取り」は、チームの透明性や再現性を奪います。チームの透明性と再現性がないと、その仕事はいつまでも同じ人がやらないといけなくなり、「やっぱりあん人がおらんなら、仕事は回らんどな。」となりがちです。ここ鹿屋にもそんなチームありませんか?
■グーグルの人事部門が発見した、チームに“意味のない要素”
Googleの人事部門は、長年にわたり、従業員の働き方を徹底的に分析してきました。
その結果、生産性・創造性・チームの幸福度に寄与しないものが明らかになっています。それがこちら:
- 同じオフィスで机を並べること
- 合意による意思決定
- 外向的な性格
- 個人の実績
- 役職や在職期間
- 期待される仕事量
- チームの人数
どれも「なんとなく正しそうだけど、実は幻想だった」ものばかり。
特に「対面でのやり取り」や「合意形成」という“日本的チームワーク”が持ち上げられがちな場面では、思いきって手放した方がうまく回ることもあるのです。
■「気合いとノリ」よりも、「ツールと設計」
チームが強くなるのは、メンバーが仲良しだからでも、たまたま話しやすい人がいるからでもありません。
- 誰が何をしていて
- どこまで終わっていて
- 何がボトルネックになっているのか
こうした情報が自然と共有されるしくみこそが、本当のチームワーク。
Slackでも、Notionでも、ふせんでも、やり方は自由。大事なのは“記録が残り、責任が明確になること”です。
「○○さんや、◇◇社長、△△長に話を通してみっで。」と、それぞれのプロジェクトにおいてキーマンとなる人との、電話での個人的なやり取りが「仕事ができるアピール」になっている人がいますが、そんなのはチームにとっては無駄です。アピール合戦はもういいです。いますぐチーム内でわかるところで聞きたいことと回答を共有しましょう。
■まとめ:「空気を読む」から、「空気を設計する」へ
鹿児島・鹿屋という地方都市でも、今や遠隔チーム、複業、リモート案件は当たり前のように増えてきました。
「空気を読む」文化から、「空気を設計する」仕事術へ。
皆さんも、そんな働き方を始めてみませんか?
📮感想やご意見は、ぜひコメント欄へ!
筆者:鹿屋ライフハック太郎
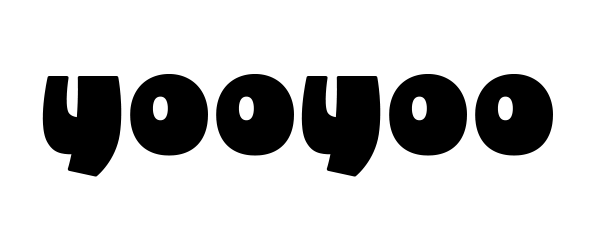
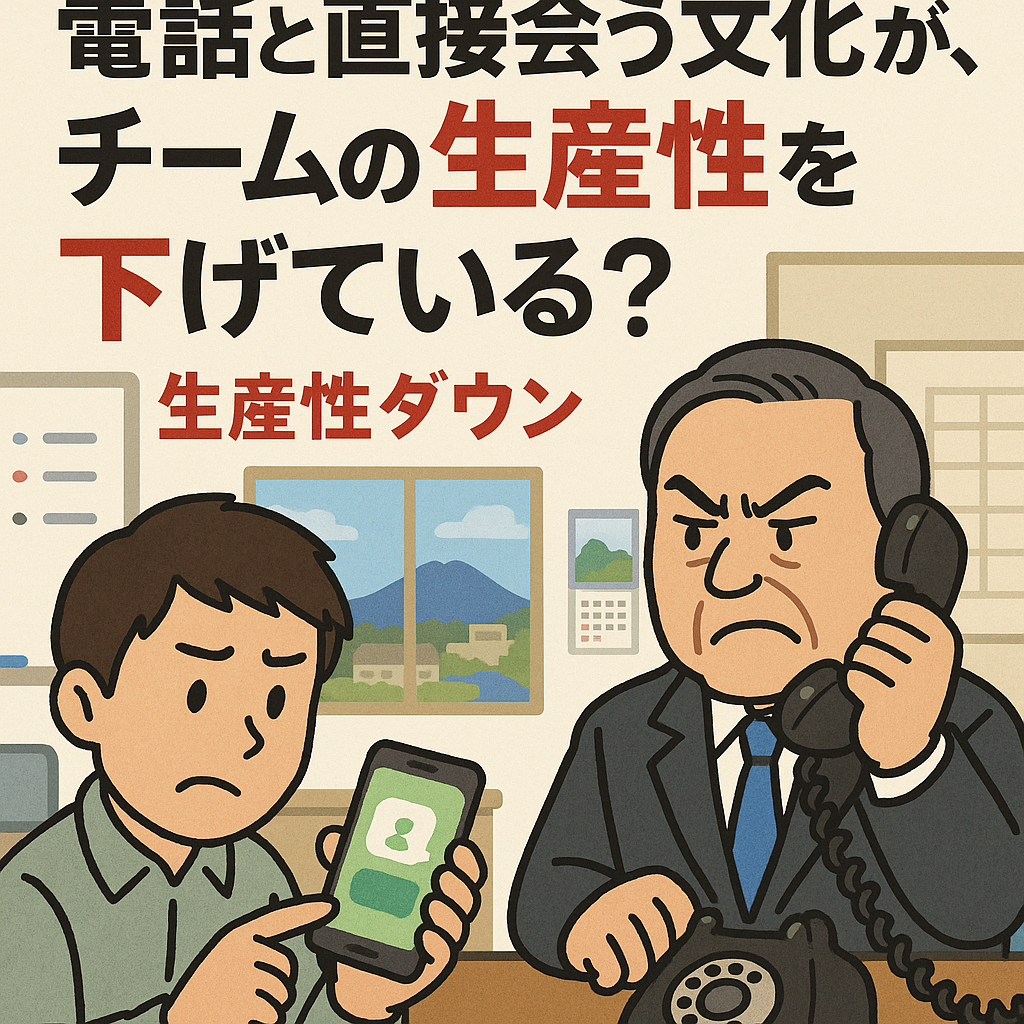
コメントを残す