文・鹿屋ライフハック太郎
1 シリコンバレーの神話は、ここ鹿屋でも実現できる?
「Google みたいなチームなんて、うちの十数名の会社じゃムリだよ」
……そう思った時点で負けです。
Google が十年かけて行った “プロジェクト・アリストテレス” という大規模調査では、「誰がメンバーか」より「どう協力するか」が成果を決める、と結論づけました。
Googleの人事部門は長年にわたり、従業員の職場での生活に関してありとあらゆる側面を分析し、生産性やイノベーション、エンゲージメントの向上に取り組んでいた。その過程で、結果が出ているチームに共通する5のポイントがわかってきました。
これはGoogleだけができる特別なことではなく、普遍的なものばかりです。言い換えれば――鹿屋の商店街にあるオフィスでも、やり方さえツボを押さえれば世界レベルのチームになれる、ということです。
2 Google 式 “5つのカギ” を鹿屋の現場に当てはめる
① 心理的安全性
ミスを隠さず言える空気。
「無知」「能力がない」「和を乱した」といったレッテルを貼られる、怯えながら働くことがない、これが重要です。自分がミスをしたときに、それを認めたり、分からないことあるときは質問をしたり、新しいアイデアを出したりした時に、それを「恥ずかしいことだ」となじったり、罰したりする、そんな人はこのチーム内にはいない、という確信が得られていることが重要です。
朝の打ち合わせで「昨日やらかした話」から始め、爆笑が起きれば合格。笑えないなら、それは空気が凍っている証拠かも。
② 相互信頼
「任せたら大丈夫」と思えるか。
それぞれの人が確実に、締め切りまでに質の高い仕事をやり遂げてくれる。そして、誰もが自分の仕事に真剣に取り組んでいる。これがチームには重要です。
鹿屋は顔が広がりやすい分、裏切りは半日で噂になります。逆にいったん信用を得れば、町全体が保証人のように機能します。
③ 構造と明確さ
明確な目標。明確な計画。明確なターゲット。何をするのか、なぜやっているのか、どうやって目標にたどりつくのか。こうした問題意識について、短期的・長期的な目標を設定し、伝達する。
漁港のホワイトボードに今日の漁獲量を書くように、プロジェクトの到達点を“誰でも指させる場所”に貼り出しましょう。
④ 仕事の意味
“Why” は人によって違う――家族に胸を張りたい、地域の未来を変えたい。動機を共有する場さえ作れば火力は倍増します。
「仕事の意味は属人的なものです。経済的な安定を得る、家族を支える、チームの成功を助ける、自己表現するなど、人によってさまざまです」
そして、それでいいのです。大切なのは仕事そのもの、あるいはその成果物に目的意識を持つこと
⑤ インパクト
「自分がやったことが何らかの変化を起こしている」と実感できること
「自分の役割に意味がある」という実感は大切です。実感していれば、自分個人の仕事の充実感が増すだけでなく、自分がチームの一員だという自覚も高まる
新サービスがヒットすれば商店街の空き店舗が埋まり、祭りの協賛金が潤う。成果が街の風景を変える。それが商売の醍醐味であり、それは鹿屋でも同じです。
3 “それ、実は重要じゃなかった”7つの思い込み
強いチームに必要なことでは別に、チームで成果をあげることに必要じゃなかったこともわかってきました。
ここ鹿屋でも、こういう効果ないことに取り込んでいるチームや会社はありませんか?これを機会に考えてみてはいかがでしょうか。その重要じゃなかった7つの思い込みは以下のようなものです。
- 同じオフィスに詰め込むこと
- 全員一致の意思決定
- 外向的な性格が多いこと
- 高学歴・個人成績の高さ
- 役職や勤続年数
- 残業時間の多さ
- チーム人数の多さ
Google の分析では、これらは成果への寄与が薄いと判明。むしろ「距離が近すぎて言いたいことが言えない」「全会一致が遅延の原因」など負の側面が目立ちます。
4 結論――鹿屋こそ “Google 超え” の土壌
鹿屋という町は、宮崎との県境までも、鹿児島市内までも車で小一時間、中心街は自転車で十分で駆け抜けられるサイズ感。この“ちょうどいい狭さ”こそ、Google 式チームビルディングの秘密兵器です。
1) 心理的安全性×相互信頼:
コンビニで誰かが買ったお菓子の話題が、昼にはオフィス全員に伝わる。この情報網の速さは、ともすれば監視社会ですが、裏を返せば「失敗の共有」が光速で行える環境です。
誤魔化すより笑い飛ばし、次の一手を議論する――これが“かのや流リカバリー”。一度信頼を得れば、同じ速さで「彼に任せれば大丈夫」という評判も広がります。
2) 構造と明確さ:
鹿屋の会社は、企画も顧客対応も一人が担う“多能工”が当たり前。だからこそ、全員がプロセス全景を把握しやすく、「うちは縦割りだから」という言い訳が存在しません。
タスク可視化に必要なのは、高価な SaaS (インターネット経由でソフトウェアをサービスとして利用できる仕組み)ではなく、錦江湾の潮風にさらされても消えない耐水ペンとホワイトボード。
3) 仕事の意味とインパクト:
都会の KPI (重要業績評価指標)はグラフ上の数字ですが、鹿屋では売上が上がると商店街のシャッターが一枚開く、高校生の文化祭が豪華になる、街にすてきなレストランが一つ増えるといった“風景の変化”で可視化されます。
この手触りこそが、Google の巨大キャンパスに匹敵するモチベーション装置です。
4) 文化としての「恥の共有」:
焼酎の町・鹿屋では、乾杯の勢いで失敗談もサラリと話せる土壌があります。失敗が笑いに昇華され、成功は同じテーブルにいる仲間全員の手柄になる。
この「恥を共有し、成果を祝う」文化が、心理的安全性・相互信頼・意味・インパクトを一挙に底上げします。
つまり、鹿屋発チームが Google を超えるために必要なのは、豪華な社員食堂でも AI 会議室でもなく――
ミスを晒して、全員でフォロー。達成したら、全員で焼肉やって、焼酎。
このサイクルを回し続ければ、桜島の噴煙に負けないエネルギーがチームに宿ります。錦江湾を吹き抜ける潮風のように、軽やかでしなやかな組織――それが “かのや式最強チーム” です。
明日の朝礼から、あなたの会社でも始めてみませんか?
参考:Business Insider Japan「最高のチームをつくる調査の意外な結果 ─ メンバーは重要ではなかった」(2025 年 4 月 25 日公開)
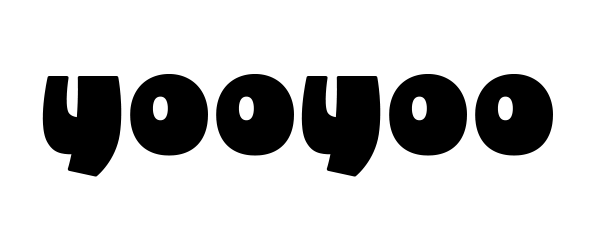
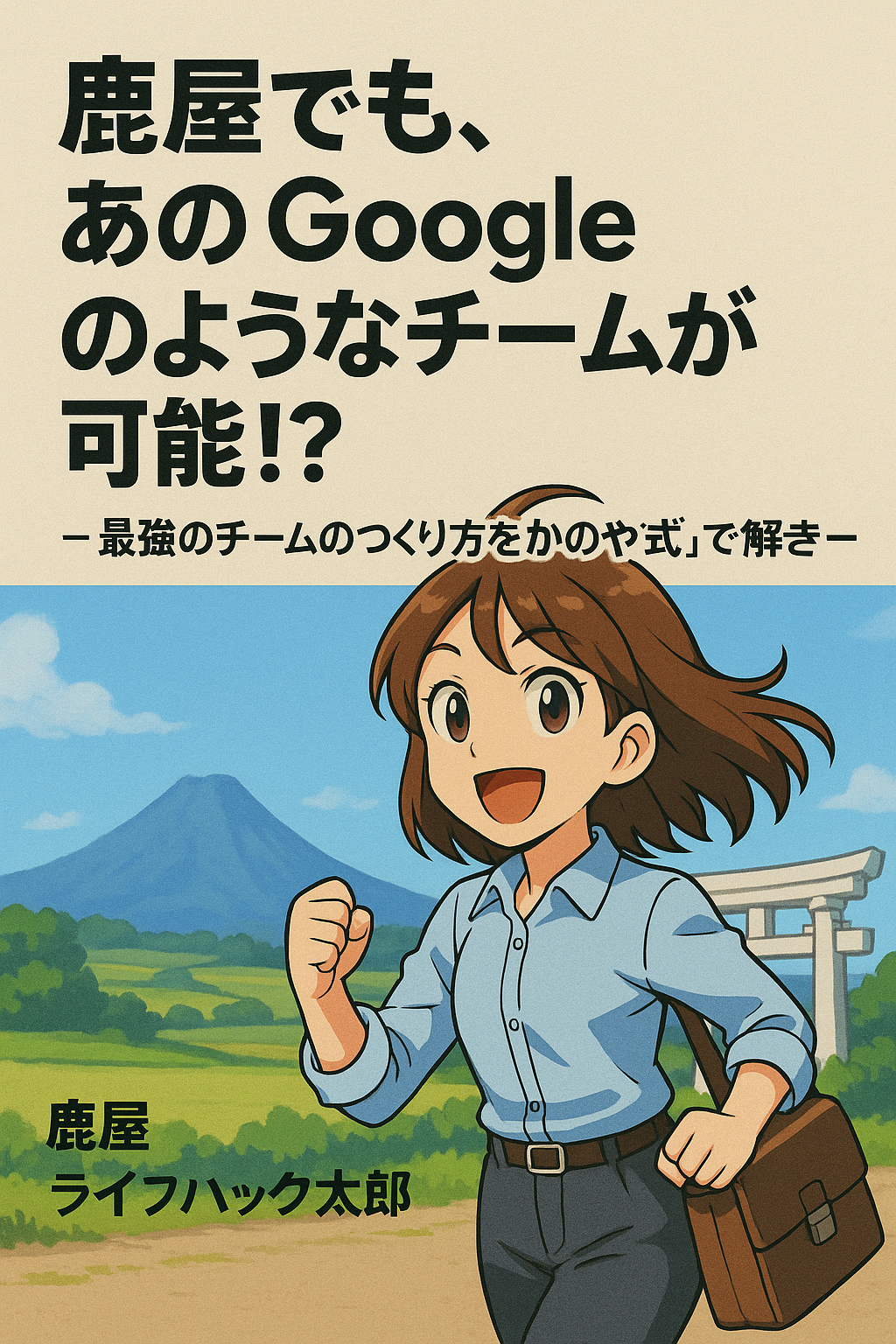
コメントを残す