(8号掲載)
8号の特集は2021年の鹿児島、大隅のニュースを中心に、集まりいただいた五人で振り返るというものです。座談会はとても盛り上がりました。その様子が少しでも紙面に反映できていたらうれしいです。『やうやう』は座談会が重要だと考えます。原発、ワクチン、ウクライナ、何かと分断を迫られるような状況が続きますが、意見が違っても同じ席で何かについて議論するということを大切にしていきたいです。
トークメンバー
米永新人 南九州新聞
躯川 恒 かのや乳児院
大浜 やうやう編集部
土屋 やうやう編集部
A 鹿屋在住
土屋 本日はありがとうございます。2021年の一年間を各新聞社の記事で一面になったものを参考にしてまとめました。それを見ながら一月から話していきたいと思います。
1月 ワクチン接種推進チーム・桜島大橋
土屋 鹿屋市の「新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム」が設置されていますね。これは南九州新聞の記事ですが、当時はどのような感じだったんですか?
米永 ワクチン接種の体制づくりができるのかと不透明な状況でした。そもそもワクチンを疑問視する声も多く、実際に僕も飲みの席で、それなりの立場にある人がワクチンを打たないということを聞いて、ちょっと議論になったりしましたね。
土屋 この話題になったので、いきなりまとめのようですが、この一年はワクチンに対する意見が人によって本当にわかれた一年でしたね。僕も個人的にも結構いろいろありました。何人かと喧嘩までいかないですけど、いろいろ言われましたね。だから、疑問に思ってるっていうより、お互い信じてることをわかり合えないなって感じがすごい強かったですね。
A それは分かり合えないと思う。
躯川 それぞれの考え方があるからね。だって、政府の陰謀論や中国の細菌兵器でどうのこうのって言う人が出てきて、そっちの人ものっかってきて打つ打たないという話になったりもする。
A ここ最近のニュースをみていると、国としては全員打ちなさいよという方向なのかな?と感じますね。
土屋 やっぱり国としてはそうなんだと思う。この前、息子と旅行に行こうとホテルをとったんですよ。打ちたくないっていう人は、確かに居場所がない空気になってきているんじゃないかなとは思いますね。
躯川 私の周りでも打たない人は少数いて、説明してもネット上の情報を信じてて、それ以上は突っ込めないですしね。あと海外みたいなロックダウンや接種券やPCRがないと通さない、店には入れないなんてこともこの国はできませんから、すべてお願いベースですよね。
米永 政府もおかしいと思う。ワクチンを接種して副反応でなにかあったときに責任を取りたくないみたいな感じで強く言えないのかなぁと感じます。でも経済を回すためには打たないといけない。非常時なので平常時と違って政治力ももう少し強く出してもいいのかな?って
土屋 例えばドイツだったら日本人のピアニストにも200万円配ったのに、日本はアベノマスクが2枚だったと話題になったんですが、この国はシステム上、政府が僕たち個人の口座や収入先を把握していないんですよね。それができている国は危機のときにぱっと支給できる。だから今回も10万円配るのにもすごいすったもんだありますよね。これについては、いろいろ憶測が飛んでますけど、おそらくただ単にできないんだと思うんです。だから一律に配るしかない。国の権力を強くするっていう方法は確かに僕も必要だと思うんですけど、じゃあ僕たちが口座とかを政府に全てオープンにするかっていったら、多分しないんじゃないかなと思います。
「やうやう」で政治家を出したいというのは全然ない
躯川 でもほら、納税や確定申告はほとんどの人はしてるから、それを紐づけしてわかるっていうのはないのかな?
土屋 僕は個人の商売してるからわかるんですけど、日本はやっぱりザルといえばザルなんですよ。だからそこを国民が受け入れるかっていうと、僕はそうならないんじゃないかな?って思ってます。
A お金をかけないけど、でも変なところには平気で使ってますからね。今回のクーポンとか、マスクの保管費とかね。
(一同) あれ、すごいですよね。(笑)
躯川 多くの国会議員のみなさんは、外で働いた経験がない人も少なくないだろうから、死に物狂いで働いている人たちの気持ちとかわかってない人も多いのかな?と思いますね。
土屋 それは鹿屋の議員も同じですよね。議員も就職活動みたいになってるように感じますね。
米永 僕は若い人や女性にもっと政治に出てほしいなと思ってます。鹿屋だけじゃないのかもしれませんが、若い人や女性が出にくい何かがあるような気がしています。だから、今回の「やうやう」座談会みたいな集まりが鹿屋市内にいくつかできて、そういう集まりの中から「私はこういうことをやってみたい、こういうことを頑張ってみたい」という声がポツポツと出て、地域政党のようなものが出来たら面白いのになーと思うんですよね。できれば鹿屋からそういう団体が何個か出てきてほしいですね。
土屋 僕自身。「やうやう」で政治家を出したいというのは全然ないんですが、ここで座談会やトークショーで議論をして、政治家になりたい人たちが、ここの議論を気にするような状況にしたい。僕はよく市議選に誘われますが僕が出たいとか、僕が何かのイデオロギーがあるということではなくて、そういう議論の場にしたいと思ってます。
躯川 ただ、鹿屋ってこの前、市長選もありましたが、若手のいろんな団体がいくつもあってすごくいい人たちだけど、鹿児島市や霧島市のように若い人たちを市長に押し上げるような動きにはつながってこないんですよね。
米永 もうあきらめていますからね。昔の嶋田市長のように民間から「候補者を出してくださいよー」と何度か聞くんですけど、「あの選挙でもうコリゴリ」みたいな感じで返事が返ってくる。
A あの、ちょっと口が悪いけど、「自分たちが中心にいて街を動かしている」と勘違いしている人たちがいるんですよ。「自分たちが鹿屋を、もしくは世の中を動かしている」ぐらいなイメージですよ。だけどその人たちがイベントをするとなったら、その関係者しか集まらなかったりする。
躯川 自己満足的なやつですね。
米永 僕がこういう場に参加するのは、経済は経済でもちろん大事なんだけど、もっと選挙とかじゃなくて、もうちょっとこう、文化とか知的なそういうインテリジェンスを感じるような鹿屋市の人たちっていないの?って僕はすごく思っていて。
土屋 この国の政治って、例えば「こども家庭庁」でも何でもいいんですけど、例えば子どものための政策を打とうと言ったときに、それが王道にはならない。何が主要になるかといったら、米永さんがおっしゃったように、まず「経済活性化」、いかに金を儲けるか。それと、一緒ですけど「集票」。この二つに関連する政策しか政治家はやる気がないんですよね。
米永 理念とか哲学とかでもっと議論が出来る場が欲しい。
土屋 2014年に出た「地域が消滅する」っていう新書があるんですが、最近ちょっと読み返しているんですけど。2014年の時に出生率が1.3なんですよね。それで、政府は2025年ぐらいまでに1.8にするっていう目標を立てたんですけど、今も1.3で全く変わっていないんですよね。
躯川 もう人口減は始まってます。子どもの生まれる数が90万人を切ったわけじゃない。お隣の韓国だって似たような状況で今の出生率が0.8。1人も産まない。
ネグレクトと不登校みたいに問題がふたつ発生しちゃう
A このあいだある過疎地域の方が「携帯電話で通話をしすぎてお金がかさんだ、もう怖くて通話ができない」って言ってて、けど周りには人がいないから、その人には必要だったりして、私たちの目が行き届かない現実がある。これが現実なんだな、と思った。もっと言うと今はヤングケアラー問題の話にもなってきているんだよね。鹿屋市でも1~2割ぐらいはヤングケアラー(18歳以下で家族の介護をする子どもたち)がいるんじゃないかと言われている。
躯川 うちが関わったケースだと、子どもがふたりいて下はまだ小さい。親はダラダラしているような家庭で、高学年のお姉ちゃんが学校に行ったら小さい子のお世話や食事はどうするんだ?ってなるから、結局この子は不登校になりました。そうすると、ネグレクトと不登校みたいに問題がふたつ発生しちゃうわけ。
A そして、それがなんで見えないのかというと、自分が貧乏だとか、困ってると思われたくないっていうのもあって、何も言わない。今年はぶっちゃけそういうのがよく見えた1年だった。
米永 僕が思うのは、やっぱり市役所に行っていろんなことを取材をしたりするんですけど、「何たらかんたらっていう国の制度が来ました」とか言って取材に行ったりすると、教える人もほとんど中身を分かってないことも多い。やらされてる。何が言いたいかっていうと、北海道と沖縄って全然ちがうんだから、それぞれの地方に合ったやり方があるはずなのに、全国一律になんでも決めてしまう。地方分権とかその辺はちゃんと議論したほうがいい。「東京一極集中」というのが日本全体の一つのひずみになっていて。東京で決めたことは、鹿児島でどうなってるかっていうところが分かっていないんですよね。
A それと、鹿屋市って、隣の町や県とかが気になりすぎていて「ここがこうやったから僕たちもこうしましょう」なんですよ。生理用品の対応もそうですよ。必ず後出しじゃんけんなんですよね。
米永 それは、仕事をしてないっちゅうことなんじゃないですか。(笑)
土屋 確かにそれはありそう。
躯川 そこは行政が行き届かないところがあるので、例えば、議員さんはあくまでも市民の代表として各地区から出ているんだから、その議員さんに現状を伝えて、議会の中でこうこうだよって言ってもらえばいいんですけどね。
米永 ただ、議会を見ていても、昔と比べてなんか眠たくなるんですよね。だから、今の政治のシステム自体がもう、本当に機能してないと感じたりする。そういった問題に突っ込めるのは議会、政治の力なんですよね。
土屋 まだ1月っていうので驚いてるんですけど。朝までかかるんじゃないかと。(笑)1月中のことで何か話したことはありますか?この桜島大橋についてはどうですか?
米永 桜島大橋推進については、簡単に言うともう20年ぐらいずっと活動に関わり、署名を行ったり募金をしたりして、お金集めてその基礎調査をしてもらったりと動いているんですけど、でもね、橋がかかるのは鹿児島市なんですよ。で、垂水市と一緒に一生懸命やったりしている中で、鹿児島市の人からのレスが何もないのはどうしてだということで、20年かかってやっと今回、鹿児島市に「桜島大橋推進協議会」ができたんですよ。それがひとつのスタートです。
土屋 今の話を聞いていたら、米永さんは桜島大橋はけっこう良いんじゃないかと思っている感じですか?
米永 いいんじゃないかっていうよりも、活動してきた中で、マイナス面を言われる人もいますが、何かアクションを起こすことで見えてくるものがある。何もしないでいてあーだこーだと言いたくない。
土屋 いやもちろんお金のことなので難しいのかもしれないですけど、桜島に橋を作っても意味ないだろって僕なんかは思うんですよね。錦江湾の真ん中を横断するような橋を繋ぐんだったらありかなとは思いますよ。桜島で繋がれても、どうなの?と。
米永 これからは内之浦のすごいポテンシャルが高い。大手企業の下請け工場誘致や民間ロケット発射の誘致がすでに動いていたりする。ロケットが発射するたびに大崎あたりの宿泊施設はすごく盛り上がる。いま北海道や和歌山あたりで行っている民間ロケットの発射実験などを本格設備の整っている内之浦に誘致すれば、今は年に1、2本しか発射していなのが、1年に4、50本は飛ばせるんじゃないかという話があって、その中に桜島大橋の架橋の話もあって、いろんなことが動いているところなんですよね。
大浜 私は橋ができたからといって大隅半島の人にどれだけメリットがあるのかなと思います。大隅から鹿児島市内へ行くだけで、本来なら大隅半島に来てもらうような文化的、観光地などの魅力がないとそうなるように思います。
米永 実はけっこう大隅半島には来ているんです。例えば、高隅山にはトレッキングで年間で二万人くらいきていますし、内之浦のロケットでは打ち上げのたびにすごい人がやってくるんですよ。打ち上げが延期になるとだから地元は喜んでる。(笑)
大浜 内之浦の人から聞いた話だと、種子島からロケットが飛ぶと、腹が立つって言ってました。(笑)
(一同)(笑)いい話だね!
2月 大隅半島の観光・女性進出
土屋 やっと2月ですが(笑)
躯川 南大隅町にホテル着工の話がありますが、知り合いが南大隅町でパイナップル農家をしているのね。パッションフルーツやアボカドも育てていて、ゲストハウスも自分で作っていて。そこに、この前EXILEのひとりが完全プライベートで来たらしいのよね。だから、興味があれば南大隅でも来るんだよね。でも志布志や南大隅や鹿屋が点と点になっていて線でつながっていないから、鹿屋はスルーで、こっちに来ることはないんだよね。鹿屋の観光事業がもっとできることはあるよね。
A 南大隅町は今、クラフトビールを女性の方がやっていて、取材にいったけど考え方がすごかった。1匹の蜂から始まるストーリー。クラフトビールの蔵元のすごい人のところで「私は真剣です」と気持ちを買ってもらって、その人の最初の弟子になったんだって。そこのタンカンを入れてビールを作ったりしているんだけどすごくおいしい。
米永 僕は佐多が大好きで、佐多岬トレッキングというのがあって、もう何人も連れて行っていて、それとバイクも大好きで、バイク好きな人って日本最南端の佐多に行くんですよね。やっぱ南大隅ってスッゴイ魅力があるんですよね。ゴールドビーチとかも最高ですよね。以前、根占フェリーがなくなったときに調べたんですけど、その当時は旅行会社のツアーのコースになっていて宮崎から大隅半島を通って笠之原ドライブインで休憩、根占から指宿にフェリーで渡って、鹿児島県を一周する観光バスが中心だったんですけど、フェリーがなくなってスパっと切れて、そこからそのコースが無くなって、その後復活できていない。で、当時の鹿屋市長に「これは大隅半島の大事なことだから。観光にとってはすごいインパクトのあることだから」という声もあったんですが、「根占港のことやろが」と言って聞いてくれませんでしたね。
躯川 さっきの桜島大橋で言っていた、大隅半島全体の流れっていうところのイメージができなかったということですね。
米永 そうなんすよ。「もう我がこっ我がこっ」という面が強いのか、常に自分のところが一番じゃないと駄目みたいな…。
A そうなんだよねー。
土屋 僕はみなさんのように内部に詳しくはないですけど、なんか鹿屋ってそんなイメージありますよね。外からは全然そう見えてないのに、自分たちは大隅でリーダーと思っているみたいな。2月は他どうですか、森さんの女性別発言とかもありましたが、女性のお2人はどうですか?
A 私は問題が発覚して「女性進出」っていう言葉が加速した気がします。
躯川 森さんって、ほら浅田真央ちゃんのことでも何かあったけど、発言全文を読むと単なる悪口じゃないんだみたいなのはある。全部切り取りだからね。だからそれこそ同じ発言者について産経新聞と読売と朝日と毎日では全然書き方が違う。
採用を決める人が男だから
A 「女性進出」って言われてるけれども課題は山積みなんだよね。子どもがいたり家庭があるってなると、コロナの影響もあって、雇用の問題を中心になかなか公平にはいかない。
土屋 南九州新聞のコラムでも書いたんだけど、例えば、今サンシャイン池崎が鹿屋市のCMをやってるじゃない。で、鹿屋で畜産をやっている女性が3人いるんだよね、それで女性3人をポスターに載せて「女性が活躍できるまち鹿屋」みたいな感じポスター作ってたり。
A 鹿屋市は今「女性進出の町」ってめっちゃ推してるんだよ。
土屋 でも、鹿屋市役所の管理職って55人いるんだけど女性は1人なんだよね。この3年間でずっと。そこが変わらないのに「女性進出」って言っていいの?っていうのはある。
A 「女性批判」とか「女性差別」という言葉が私はあまり好きではなくって、そもそも実力があれば、いけるじゃんって話。それは森さんの話にしてもそうなんだけども、結局セクハラだとか女性差別だとかっていうのばっかりで男性差別や男性が受けたセクハラはあまり大ごとにはならず、結局女性がされることばかりが問題って言われるよね。
土屋 「実力があったら女性も上に行けるだろう」っていうのは、俺もそうだと思ってる。今の社会はそうなってるはず。そう信じたい。
A 私はそういうふうに思っていたいけど、女性自身がそういうことを言い過ぎて逆に自分たちの首を絞めてしまっているところがあるようにも思う。
大浜 私はそうは思っていないんですよ。もちろん実力があれば上に行けるんですけど、上に行ける可能性は男女比で比べると、絶対的に男性のほうがパーセンテージは高いですよね。なぜかというと、採用を決める人が男だから。同じような能力の人で男と女がいたら、女性が出産とか子育てがあって、男性は大黒柱という考えがあるから、男性を絶対上にあげるんですよ。それは、ホモソーシャルと言って、男社会の連帯意識でもある。だから、クオータ制みたいなものを強制的に取り入れて、女性は表舞台に出たくないって言うかもしれないけど、とりあえず頭数揃えて機会さえ与えてくれれば、慣れてくるし能力も上がってくると思うんです。だから、無理やりにでもクォーター制とかパリテとかを取り入れたらいいと思っています。フランスを例に出すと、パリで女性の参政権が与えられたのは、日本より1年遅いんですよ。今は女性の議員数も50%で日本と全く違う。政治の部門では日本はジェンダーギャップ指数は日本はたいへん低い。
土屋 ちょっと調べたんだけど、採用の時点では市役所も2:1ぐらいなんだよね。だけど、管理職55人のうち女性1人っていうのはあんまりで。ただ、じゃあ女性が途中で辞めているかっていったら、男女とも平均勤続年数は30年以上なんですよね。だから、男だけが残ってるってことは絶対ないはずだから、管理職55人のうち女性1人っていうのはあんまり。それも今年はじめてなはずだよ。女性管理職ができたの。
A 聞いた話ですが、今の市長が「女性活躍」をすごく言っているかららしいです。だけど結局それも世間が言ってるから鹿屋市もやってます感を出してるだけですよね。
米永 「男女共同参画」っていう言葉が出てきたのが、多分もう20年以上前なんですよね。僕がその時すぐ思ったのは、「これって女性というよりも男性の問題」と。以前、鹿屋市の市議に女性が2人いたんですよ。そして、その2人が辞めて、勝手に「女性議員をつくる会」で声をかけました。そのときに思ったのは、女性の方が人口も多くて、そこだけ考えると女性がもっと増えてもいいかと思うんですけど、女性の議員は少ない。立候補する余生も少ないし、女性が女性に投票するかといったらそんなことはないんですよね。配偶者や職場とかに影響を受けている印象です。
大浜 女性が政治家になったり社会に進出していないから、声が届かないから、反映されないんじゃないかって私は思います。ほとんど全ての問題が結構それで解決されるんじゃないかなって思うんですよ。例えば、学級会で物事を決めるのが全部男子というのはありえないのに、社会は全部男の人が決めたルールで動いてて女性が生きやすいはずがない。子どもを産ませたかったら、女性の社会進出も出生率も高い北欧のように、女性を支える社会システムを考えないといけないと思う。「女性の幸せは、社会の幸せに直結している」って私は思っています。
米永 付け加えてなんですけど、多くの議員の中で女性議員が、一人で出来ること、それも初めてだとなかなか活動しにくい。でも女性議員が3人いれば、例えば女性に関わるような教育と環境と福祉」の三つをそれぞれ4年間の任期の中で、最初の1年間はみんなで勉強して、その次の1年で教育、環境、福祉の順番でそれぞれの役割を決め、否決されてもいいから女性ならではの条例提案ができないか。3人いれば条例提案できるんです。やっぱり女性特有の着眼点、男性には分からない部分っていっぱいあるわけじゃないですか。そこってね、もう繰り返しなんですけど、男性がそこをちゃんと見てあげないと、女性の力だけじゃ絶対できないので、だからそういうことも含めて、もっともっと僕は政治を志す女性が増えてほしいと思いますね。ただ、女性がというよりも、圧倒的に多い男性議員による、議員発案の条例とか無い。そこが一番問題なのかもしれませんが。
4月 廃校・学校給食・八千代伝・出産支援体制
土屋 4月は、南大隅町長選挙もあり、「やうやう」でも特集して、多くの反応をいただきました。学校の統廃合の話も多いですね。
米永 僕が学校に関してすごく思ったのは、学校給食の問題があるんですよ。大隅半島って食がすごく豊かなので、例えば海の学校には海のものをちゃんと給食に入れて、山の学校はやっぱり高隈山の美味しいものとか入れて、子ども達に地元の食材を食べさせたい。学校に給食室があればそういう希望が叶うじゃないですか。ところが、南部と北部の大規模給食センターで8000食とか1万2000食を作るとなると、それができなくなる。南部センターが出来る時、いろいろ調べたんですけど、例えばお米、学校給食会という組織、校長上がりのペーパー組織を経由、肉についても市内の肉屋を聞いて回ってみたんですけど、そんないっぺんには出せないと、口を揃えて言う。自校方式で運動している人たちをずっと追っかけて取材もしてきて、教育委員会とかに直訴するんですけど、結局「これはもう決まったことですから」の一点張りで。じゃあ決定前に市民に投げかけたんですか?って。そういうことは無しで決めてい、その時の運動していた保護者らの忸怩たる思いをずっとみてきました。そして最近ですが、古江、菅原、高須、浜田の海岸線の学校も相次いで廃校になった。海の学校として1校残すようなこと、その地域の文化や活性化も含め政策的に本当に必要なことだったと感じて、残念でなりません。
A 結局、学校が統廃合する前に利活用できるところを探しているというのは、行政が「学校がなくなった後はこういう企業が入ってきますよ」という安心感を与える説得材料になってる。最終的には、そこに住んでる人の意見が一番重要視されるんだけれども、でもやっぱり行政側としては学校数を減らしていかないといけないっていうところもあるわけで、何か代案みたいなのは常に考えておかないといけない状況なんですね。
土屋 僕も子どもの給食を見ていると思うところがありますね。僕たちのときの給食って結構うまかった。給食室があって、おばあちゃんたちが作ってくれたからそうなんだけど、今は給食センターだからね。うどんの日にパンとジャムがついていたりするし、僕はうどん屋だけど、うどんとジャムパンのセットは日本中探してもそんなうどん屋ないでしょうね。(笑)
米永 「大隅は食が豊かで~」って農業関係者が一生懸命言っているのにね。
A 出産支援体制の話もさせてください。まず生むところがない。今は王産婦人科と寿レディスクリニックしかない。あとは、たまにちょっとリスクのある人たちが大隅鹿屋病院に入ったり。
土屋 この問題は結構深くて、やっぱり女性議員が増えないとそういうことも大事ってならないんですよね。だから例えば、妊娠がわかって病院に検査に行くのって健康保険が利かないっていうことは、男性の多くは知らないんじゃないかな。出産一時金も健康保険を払ってる人だけなんですよね。だからこんなに貧困化してるときに健康保険払えていない若い人たちはたくさんいて、相談もできないからいざ産むってなったときに家で産んだりとかして、こんなに泣くなんて思わなかったと口をふさいで赤ちゃんが死ぬ。いわゆるゼロ児死亡の問題ですね。
A そう。だから本当の意味での出生率を上げたいって思ってたらまずそこから着手すべき。「鹿屋市としても出生率を上げましょう、何とかその10万人を切らないようにしましょう」っていう話をしてるけれども、じゃあこの現状をどう捉えているんですかって聞いたら、「鹿大の先生が週に何回か来てる」みたいな回答になる。
土屋 4月はその他どうですか。なんか垂水の八千代伝が頑張っているよね。今回知ったんだけど、20日の八千代伝のイベントは、ホリエモンと一緒の企画で出たんだね。和牛マフィアっていうのがホリエモンのやつなんだね。
大浜 とにかく「八千代伝」は今評価が高いですね。
土屋 僕の友人の料理人も「八千代伝が良い」って言っていましたよ。
5月 ソロキャン・日置市長の永山さん
土屋 どうしてもちょっと違う話が出てくる。さあ、5月。
A 5月はちょうど連休でコロナが少しずつ収まってきたタイミングで、ソロキャンとかキャンパーが増えた。東串良の「丸山公園」「ユクサ海の学校」とかも100人ぐらい来てたとか。キャンパーが増えるのはいいんだけど、マナーができてない人たちも増えているから、火の始末やごみの始末などもしっかりしてもらいたいとのことでした。
米永 日置市長の永山さんが県内最年少で首長にというのは面白い記事ですね。それでいうと、奄美の市長選も若い安田さんが42歳で当選しましたね。彼が20代のころですか、鹿屋のイベントでお会いしたことがあり、その頃から政治家になるような雰囲気でした。奄美は去年世界遺産にも登録されましたね。すごいですね。
6月 行政と民間から作ってる
A 6月はちょうど聖火ランナーの時期でしたね。
土屋 あとは鹿児島県のワクチン接種のネット予約システムがダウンしたっていうのがありましたね。みんなが殺到して結局1人しか予約できなかった結果に終わっちゃったんですよね。
A あと、たしか6月は鹿児島ではじめて男性の育休を取得するように制度が動き出したはずです。
土屋 この国って結構、民間が自分たちで作っているところがあって、例えば大河ドラマの渋沢栄一、文芸春秋は菊池寛。他にも福沢諭吉とか、やっぱり民間から作ってるっていうのはやっぱこの国の一つの文化ではあるんですよね。だから男性の育休に限らず、民間から危機意識とか信念をもって変えていくっていうのは一つかなと僕は結構思ってる。行政は大事だし、影響も大きいのかもしれないが、結局民間の方で変わっていかないといけないのかな、みたいには思う。
A SDGsって言うとお金が入るし、NPOも立ち上がりやすいしっていうのもあって。国がもうSDGsを掲げてしまってるから、国からのお金を取れるって思っているから、やっぱり経営陣たちはSDGsと言えば儲かるぜっていうのがあって動いてるでしょう。
米永 だから、僕はバッジをつけてる人はうさんくさい人たちだと思ってるんですよ。
A そうそう、バッジをつけている人に「じゃあSDGsの17番まで言ってください」って言ったこともありますよ。(笑)
7月 行政と政治。ズームで問題解決できたら苦労しない
土屋 7月ですが、飲食店がコロナを蔓延してるっていうのが世界的に浸透していて。特に接待が伴う夜の飲食店でね。で、僕はうどん屋なんで昼間じゃないですか。その実感として、多くの人はコロナって夜に移ると思ってる感じがするんですよね。(笑)夜、酒を飲んだらうつるみたいな。
大浜 満員電車に乗って会社に行くのにね。だから完全にスケープゴートにされてるんですよ。
土屋 お酒が悪いとか、ライブが悪いみたいな感じでね。いやもちろんね、それはもちろん蔓延するんですよ、窓とかないし。それは一部事実なんだけど、でも大きなざっくりした網で規制して、「ここが悪い」と言って、それで安心させるっていうような雰囲気がすごい強かったなって思う。だから、こういう状況だから、反ワクチンの人とかの気持ちはわからんでもないんですよ、やっぱり。もし僕がもし居酒屋経営やってたら、多分そうなると思うんだよ。ふざけんなってなる。
A いろいろと矛盾してるんですよ。例えば打つ人と打たない人っていうところが出てきて、それぞれの理由は分かるんだけど、じゃあ世の中がどうなっていったかって言ったら、学校は休校になったけど学童はあって、幼稚園は認定だからあける。それっておかしいよね。
土屋 日本政府の統治能力がそんなに駄目なのかって僕には分かんない。あまりにも複雑すぎるからこの社会を日本政府って結構簡単な方向に行くんですよね。さっき言ったように、夜の街が悪いとか、学校を閉鎖すればいいと。だけど学童はOKとか意味不明な政策を打ったりするから、これはどう考えても政府が怪しいよねって陰謀論に行くっていうのも十分わかる気がする。
米永 話を鹿児島県に戻すと、今の政策決定を見てみると、三田園さんは別ですけど、他は自治省とかからの天下りなんですよね。鹿屋市も中西さんは県から来て、問題は政治というよりも行政能力はあり、処理する能力はあっても結局政治としての「決定」が弱いと感じてます。議会もそれに追従しているからなおさら、政治ができてない。
土屋 いや、おっしゃる通りで、ワクチン100万件って誰もできないと思っていたけど、国はやったんですよね。行政ってそういう力はすごくあるんですよね。だから問題があって処理はできるんだけど、今度は例えば少子化とか女性の問題があるときに何か新しいことを考えろというのができない。せいぜいズームでワークショップですからね。もう、それはわかったって。ズームで問題解決できたら苦労しないよ。(笑)
米永 行政と政治の違いっていうのは、行政というのは法律に則って粛々とそれを執行していくわけじゃないですか。で、政治っていうのは、法律とか政治と現実がおかしくなった時にじゃあこれおかしいよね、政治で法律を変えましょう、というのが政治なんですよ。ですけど、今は鹿屋もどこも全部行政一色になっちゃってる感じで、そこの区別が見えにくい。なので機能しにくくなってきてる。しかも、そういう議論ができる人もあんまりいないし。行政しかやってない、政治をやっていない、そういう町は発展しないと思います。
さっき言ったその一言に尽きると思います。「行政なのか、政治なのか」って。だから今、官僚が強いというのもあるし、行政が勝っちゃってて、でも本当は逆なんですよね。こういう非常時というときこそ政治が動かさないといけないのに。
土屋 知人が垂水市役所に勤めていて、担当課長が不在の時に鹿屋市の市議から電話があったんですよ。市議は「垂水が進めている〇〇計画について話が聞きたい」と。そしたら、その課長、〇〇の計画について調べ始めて、「市議からってことは、議会にかけるってことだから、事前に鹿屋市の行政に伝えておかなきゃいけない」っていうことで、わざわざ鹿屋市の課長に電話して「△△市議から〇〇計画について問い合わせがあった。これについては、このように説明しておけばいい」って鹿屋市の課長と口裏を合わせてたらしいんですよ。(笑)
米永 議員が地域住民の代表として、条例を提案したり制度的におかしいところを指摘して、うまく変えていくということをしないといけないのに、議員が行政マンより勉強をしていない、行政マンに強く言えない部分が見え隠れし、市議会議員が行政マン「以下」になっちゃっているんじゃないかと思うところもある。
土屋 同年代で知り合いの市議会議員が何人かいるんですが、例えばSNS上で、このコロナ禍で何かしら発言があってもいいと思うんだけど。まったくない。叩かれたりとか嫌だろうけどさ、この町にはこの問題があって、こういうふうに持っていかないといけないっていうことを発言するのは、どう考えても代議士しかいないわけだから。
リナシティについては言いたいことがいっぱいある。
米永 僕は20数年間、3月6月9月12月、いつも議場に行って議事をずっと見てきました。(今はネットでも見るけど)昔は、なるほど勉強になるなみたいなところがあったんだけど、今は「言って、答えて、はい分かりました」で終わっていて、ただの確認。それだったら、総務関連なら総務課に直接行ってそこで調べれば済むよね。議会は3日間拘束する、言い方は悪いけどこれで拘束されるほうもしんどい。以前は、議長の立場で、また議運などで指摘する先輩議員がいたり、そういうので議場がもっとイキイキしていたような気がする。今はそういうのがなくすっごく平和。「今この議場で、発言することなの?」っていう内容も。
土屋 去年の忘年会で会った「のぐちさん」。彼は鹿児島市で一人でやっている。個人だから会派もできなくて、でも僕の印象ですけど彼は一人でバリバリやっているイメージ。ただ、のぐちさんも怒られるかもしれないけどひとりだから限界もある印象です。
A 私は例えば、鹿屋市の市議会議員のために市民が議員たちに物申す会みたいな。(笑)そういうことが必要ですね。こういう座談会を重ねていってみたいなことがとても大事なことだと思うんです。
土屋 僕たちは忘れがちなんですけど、主権は僕たちだから。
米永 その中でも、繁昌議員はリナシティの問題をずっと問い続けていて、そんな議員が少なくなってきている。昔の議会はもっと面白かった。いろんな意味で。
大浜 私もリナシティについては言いたいことがいっぱいある。
A 私も!(笑)今後、リナシティはどうなるんですか?
米永 リナシティの場所は、土地や建物の権利者が100人ぐらいいたんですよ。で、そもそも「再開発」っていうのは、その多くが再開発の床を取得してその中でやっていくということだったんですけど、結局100人中の90何人はお金だけもらってそこに戻らず、再開発でなく再出発をされるということになった。残された人はとても苦労している。元々は市場みたいなのを作りましょうという話があったのに、結局ああいう大きな建物がドンとできてしまったんですよね。
A あとは、私たちが知っておかないといけないのは、私たちの財布からいくらずつかリナシティにお金が流れているっていうこと。今は年間の維持費が2億3000万円ぐらいかかっていることは知っておいたほうがいい。リナシティは、実際私たちが一般で使おうと思ったら、それはもう忖度がひどくて。大変使いづらい!
そうそうそう。(全員同意)
米永 焚き火ライブとか最初はやっていたのも、今はもうできないんですよね。それで、あそこでフリマみたいなのをやろうとしたけど制限が多くて、まイオベントで食に関わることも「ここは消防法上、火が使えません」など言われたり。
土屋 僕の友人なんて3回行って3回ケンカしてましたよ。そこではリナシティは指定管理者が変わらないとダメって言われています。こんな状況でいまの指定管理者は失格です。
米永 10年経ったら補助金の縛りがちょっと溶けてくるとも言われていて、「10年経ったら好きなことができるよね」ってみんなで言っていたのに、もっと使いづかいのかな。
土屋 せっかく良いスタジオとかあるのに、屋上もすごくいいのに、全然使われていないですよね。
A 県外から来た人が、リナシティのことを「市の墓標」って言ったんだよ。それほど地域の中で機能していない。
土屋 やっぱり行政の問題なんだな。そして、その行政に文句を言わない政治家の問題なのかな。
A リナシティはもともとは「地方創生」の流れで出来たんだよ。でも創生でも何でもなくなってきているから、もう潰して駐車場にでもしたほうがよっぽどいいんじゃない。
土屋 本当はこういうことって隠しちゃいけないんだよね。主権は自分らにあるんだからね。
8月 9月 オリンピックが終わり
土屋 オリンピックが終わりましたね。この時期がコロナが一番ひどかった時ですよね。東京で1日5000人とか、まんぼうもずっと出てましたね。他には、石橋の問題とかも出てきましたね。
米永 僕は橋のたもとの住人から話を聞いたり、保存会の人たちと話をしたりしてきたけど、もう橋だけの問題じゃないんですよね。これは周りのことを全部含めたことであって、まずは河川管理がまずかったというところからスタートして、ちゃんと河川管理のことをした上で橋のことを考えないといけないのかなと思っています。
10月 大隅の女性議員・鹿児島のSDGs
土屋 川内原発が40年超えての稼働がきまりました。九州初らしいです。
米永 だからこのコロナである程度感じている人が結構多いんじゃないですかね。今までの経済優先論理でやってきて既得権のあるところがどんどんまた大きくなっていくみたいな状況に限界がきてると。コロナがそれを教えてくれるみたいなところになっていて、ここからまたガラガラと変わっていくのかなみたいな気がするんですよね。
土屋 エネルギー政策はまた今からちょっと変わってくると思いますよ。そのほかでいえが、米永あつこさんが、衆議院選挙に社民党から立候補しました。
米永 面白いのは女性議員が、南大隅も女性町議が二人、女性がちょっと増えてるんですよ。垂水がやっと1人。垂水の歴史の中で今まで女性は1人もいなかったんですよね。
土屋 僕もそう思いますが、米永あつこさんにはこのやうやうでインタビューもしたし、たまたま休みだったんで出陣式に行ったんですが、やっぱり国政の出陣式ではないなって思いました。いろいろと厳しい状況なのでしょうが、勝つつもりあるのかな?って。立地的にも状況的にも。
あとは、鹿児島の大学生(20)中村涼夏さんが高校3年生のとき、SNSでグレタ・トゥンベリを見て、『なぜ大人は動いていないの」と思うようになったと、話題です。「なぜ、大人は動いていないの」というのは、「それは大人になったらわかるよ」と思ってます。最近のSDGsの関係で若い人たちがあまりにも取り上げられすぎていると、僕は思ってます。
これは朝日新聞の抜粋なんだけど、この20歳の子って12歳下の妹がいて、その「妹の未来への責任感に突き動かされた」とか言うんだけど、20歳の子に8歳の妹の責任を感じるとかやっぱおかしいじゃんどう考えても。
大浜 いや、それは違うと思う。理論で考えたらそうなるでしょ?
土屋 僕は、中村さんとかグレタさんは真剣だと思ってるし、環境問題も大事だと思っているよ、本当に。SDGsなんてやめろみたいなことではなくて、こういうのは個人がメディアで注目されても意味なくて、問題は社会運動として実態があるかどうかだと思う。「20歳の女の子が8歳の妹のために動く」って、20歳なんてただの若造ですよ、まずは自分のことでは?やっぱり賛同できないよ。
大浜 私は全然賛同できるけど。やっぱり代案がなくても意見を発することは重要なことでしょ。
米永 今のマスコミって、なんかすごく今ちょっと変っていうか、取り上げ方がおかしいところがあるんですよ。週刊誌とかも、情報をとりに来る時もあり、それで、例えば豚コレラが出たときに豚舎を紹介してくれと言われて手配したことがあったんだけど、記事はすでに出来上がっていて、何かあったときに写真を使う感じなんですよね。結論ありきなんですよ。それで、写真がポンと使われて、鹿屋の農家さんから「こんなこと言っていない」ってなったんですよ。だから、注目を集めて記事を取り上げるということも含めて、「この捉え方は本当にこれでいいのかな?」っていうところはありますね。
土屋 繰り返しになるけど、やっぱり運動として、さっき言ったように、「大人はわかってない」っていう運動は、やっぱり先がないと思う。だって、あなたも大人になるわけだから。
大浜 だから、そういう大人にならないように今からやっていこうっていうことじゃないの?
土屋 いや、だけどそういう大人になっちゃうんだよ。学生運動とかもみんなそう。みんな大人になっちゃうんだよ。
土屋 あとは株式会社カナザワさんが鹿屋市に二千万円寄付。さすがですね。
11月 ロペス薩摩さんのRIZIN
土屋 11月、クレーンでつるした事件、これ熱いよね。あとはロペス薩摩さんのRIZIN出場ですね。
躯川 これは夢がありますよね。市長表敬もありました。
12月 最後に鹿屋市の政治
土屋 もう最後で、12月はそんなに話題もないので、この先の鹿屋市について話したいと思います。今日の話はかなり市議の重要性があらゆる箇所で見られるという内容だったように思います。最近は選挙に出ようと思うような、若手の人たちって全然いませんよね。
躯川 それで言えば、やっぱり後進を育てるのがすごく大事で。
米永 鹿児島って郷中教育をやったわけじゃないですか。やっぱり教育ってすごく大事なことで、こういった話をすることを若い人たちにどう伝えていくかっていう縦のつながりみたいなところを大事にしていきたいですね。僕が40ぐらいのとき、誰かにまあ、いわゆる「おせ」と言われる人に相談したくても、なかなかできなかった。僕ができるかどうかは別にして、こうやってこのような場所に呼んでいただいた時には行くようにしていて、自分の意見も言うようにしてます。やっぱり若い人たちを育てていくようなこの流れができれば、この町が何かこう整っていくのかなという気がするんですよ。
躯川 米永さんの後を継ぐような人がいないと、行政がやってることを言われるままに流すニュースばかりになってしまいますよね。イエスマンばかり。
米永 ただね、例えば議会っていうのはやっぱり過半数で決めちゃうんで。例えば委員会の中でもやっぱり過半数を取らないといけない。で、やっぱり一匹狼だと大変なんだよね。市長とかだったらいいんですけど。でも、そういうことを分からない人が多いから、「それって大事なことでね、だからグループを作っていかないといけないんだよ」ということを教えていかないといけないと思ってます。
土屋 本日はほんとうに長い時間ありがとうございました。
(一同)ありがとうございました。
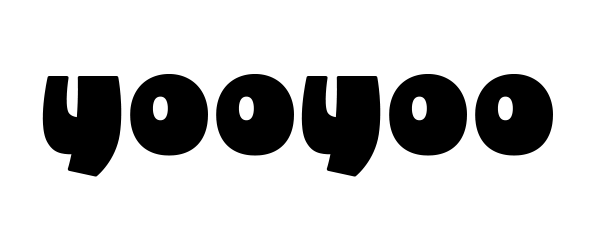
コメントを残す